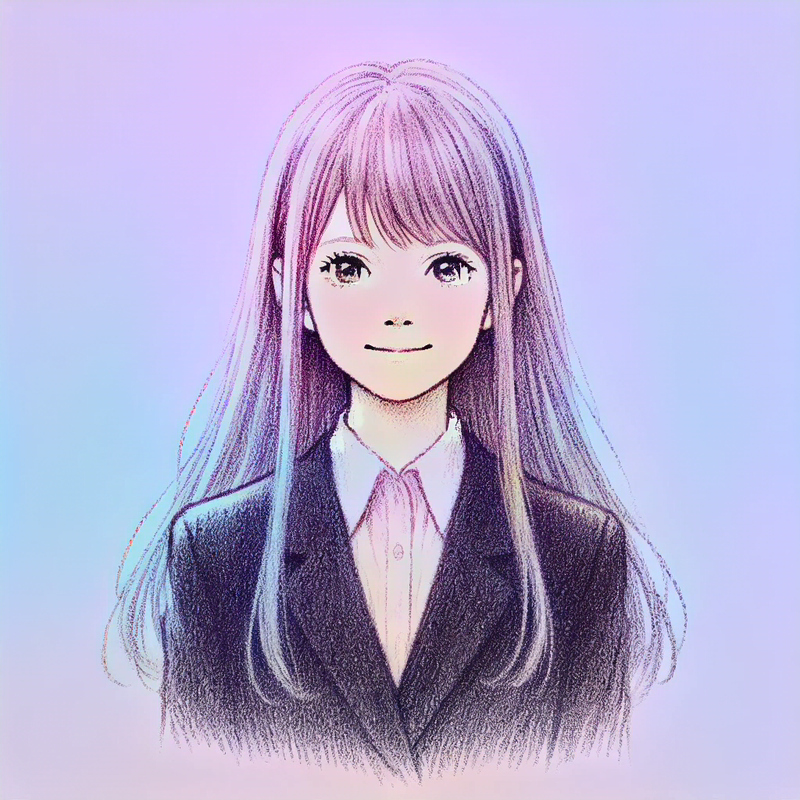今回は、Xで知り合った方の体験談です。
大変明るい印象の方で、コンサートの話や昔懐かしい話などをよくつぶやかれています。
今回、大変貴重な、ピアノをしたことで統合失調症の症状がよくなった、とい体験談をいただいたので紹介します!
はじめに
保健師として働いていた2021年の秋、私は仕事中に突然、幻聴や幻覚に襲われました。
頭の中に聞こえる声や、実在しないものが見える体験は、それまでの「普通の生活」を一変させるものでした。
気分は沈み、希死念慮にもとらわれ、自分が壊れていくような感覚に包まれました。
「患者になる」ということ
当初は仕事を続けようと必死でしたが、家族のすすめもあり、退職と入院を決意しました。
入院生活では、携帯電話の使用や外出の制限など、日常の自由が失われていく感覚がありました。
専門職として人を支える側だった私が、今度は「支えられる側」になる──この役割の変化に、戸惑いや無力感を強く感じたのを覚えています。
ナラティブ研究の文献では、こうした「アイデンティティの断絶」こそが、精神疾患の語りの中でしばしば中心になります(Deegan, 1988)。
私自身もまた、「誰でもない存在」になってしまったかのように思えました。
音楽との再会
退院後、作業療法(OT)や軽作業のアルバイトを始めながら、医師の許可のもとで、好きな音楽を聴く時間を持つようになりました。
やがて、学生時代に習っていたピアノを再び弾いてみたいと思うようになりました。
ピアノは、楽譜を読みながら両手を動かし、感情を込めて表現する総合的な作業です。
研究によれば、音楽療法は統合失調症患者の認知機能や情動安定に対して、短期的にも長期的にもポジティブな影響を与えることが報告されています(Chen et al., 2024;Wang et al., 2023)。
とくにピアノ演奏は、集中力や記憶力、判断力などを複合的に刺激し、脳の活性化につながるといわれています。
私にとってピアノを弾く時間は、ただの「趣味」ではありませんでした。
それは、自分自身が「私」であると感じられる、数少ない貴重な瞬間だったのです。
私にとっての回復とは
ナラティブ研究では、回復とは「症状が消えること」ではなく、「再び意味ある人生を生きること」だと定義されます(Davidson et al., 2005)。私にとって、ピアノとの再会はまさにその回復の象徴でした。
もちろん、症状が完全になくなったわけではありません。しかし、音楽に集中している間、私はもう「病気を抱えた人」ではなく、ひとりの「表現する人」になれるのです。
何かに熱中できることは、人生を豊かにしてくれる──
私はそう信じています。
音楽に限らず、ご自身の好きなことを探してみるのはいかがでしょうか。
よくある質問(Q&A):統合失調症と脳機能の向上について
Q1. 統合失調症でも「脳を鍛える」ことはできますか?
A. はい、可能です。
統合失調症は脳の情報処理や注意、記憶に影響を与えることがありますが、音楽、運動、読書、対話などの活動を通して、認知機能をゆるやかに鍛えていくことができます。
特にピアノや楽器演奏、囲碁・将棋、手作業、料理など、「考えながら手を動かす」活動が有効だといわれています。
Q2. ピアノ演奏が脳に良いって本当ですか?
A. 科学的にも裏付けがあります。
ピアノ演奏は、視覚(楽譜を読む)、聴覚(音を聞く)、運動(指を動かす)、思考(次の音を予測する)を同時に使うため、脳の広い領域が活性化されます。
最近の研究でも、ピアノなどの音楽活動は注意力・記憶・処理速度の改善に効果があると報告されています(Chen et al., 2024)。
Q3. 音楽療法と自分でピアノを弾くのは何が違いますか?
A. 音楽療法は専門家のもとで行う治療ですが、自分で弾くことも十分に意味があります。
音楽療法は計画的・臨床的な介入ですが、自分のペースで好きな曲を弾くという「自発的な活動」も、認知機能や感情の安定に効果があります。
むしろ、「やりたい」「楽しい」と思える活動であることが大切です。
Q4. どうすれば自分に合った脳トレ的な趣味を見つけられますか?
A. 「好き」「なんとなく気になる」から始めてOKです。
無理に「脳にいいから」と始めるより、少しでも楽しさや没頭できる要素があるものを選びましょう。
ピアノのような楽器以外にも、パズル、ガーデニング、散歩、イラスト、日記、料理、読書など、日常の中にたくさんの選択肢があります。
Q5. 続けられるか不安です…
A. 完璧を目指さず「一日5分」からでも大丈夫です。
統合失調症の回復には波があります。調子がいい日は集中できても、悪い日は手につかないこともあります。
そんなときは、「やる・やらない」よりも「思い出す・興味を持ち続ける」ことの方が大切です。
Q6. スマホの音ゲーでも脳にいい効果はありますか?
A. はい、適切に活用すれば効果は期待できます。
スマホの音楽ゲーム(いわゆる「音ゲー」)は、
- リズムに合わせて反応する集中力
- 目と手の協調(視覚と運動の統合)
- 反射的判断(即時処理)
を鍛えるのに役立つといわれています。
特に、テンポや難易度を調整できる音ゲーは、脳の処理スピードや注意力を刺激します。ただし、やりすぎると疲労や不安を招くこともあるため、時間を決めて楽しむのがおすすめです。
「遊びながら脳を使う」感覚で、音楽に親しむ入り口として活用してみてください。
以下のボタンを押すと私のnote記事へ飛びます。このnote記事では、宗教的視点から今回の体験談を考察してみました。ぜひ、お読みくだされば幸いです。
参考文献
- Chen, W., Yu, L., Zhang, Y., et al. (2024). Five‑week music therapy improves overall symptoms in schizophrenia: Evidence from EEG and symptomatology. Frontiers in Psychiatry, 15, Article 1358726. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1358726
- Davidson, L., O’Connell, M. J., Tondora, J., Lawless, M., & Evans, A. C. (2005). Recovery in serious mental illness: A new wine or just a new bottle? Professional Psychology: Research and Practice, 36(5), 480–487. https://doi.org/10.1037/0735-7028.36.5.480
- Deegan, P. E. (1988). Recovery: The lived experience of rehabilitation. Psychosocial Rehabilitation Journal, 11(4), 11–19.