親孝行という言葉に苦しめられてはいませんか。
罪悪感で親を捨てることができないという人は多いですよね。
ところが、よく調べてみると、親孝行という教えは国家統制のための教えであり、個人の幸せのためではありませんでした。
今回は、親孝行の元ネタである儒教の歴史と教えについて語っていきます。
儒教の起源と親孝行の関係:その歴史的背景を探る
「親孝行」という言葉は、日本や東アジアにおいて深く根付いた価値観の一つであり、その思想の起源は儒教にまでさかのぼります。
儒教は紀元前6世紀頃、中国の思想家・孔子によって体系化されたもので、家族や社会の秩序を保つための道徳を重視する教えでした。
その中でも「孝(こう)」、すなわち親を敬い尽くすことは、儒教思想の中核をなす概念の一つとして位置付けられています。
本稿では、儒教の成り立ちとその歴史的背景を探りながら、親孝行という教えがどのように発展してきたのかを考察します。
儒教の起源:戦乱の時代に生まれた教え
儒教は、中国の春秋戦国時代という混乱の中で誕生しました。
この時代、人々は戦乱や政治的な不安定さに苦しみ、社会の秩序を取り戻すための新しい価値観が求められていました。
儒教を確立させたのは孔子という人です。
孔子は、もともと国家のための官僚になりたかったのだが、なれなかったのです。
こうしたことから、そもそも孔子という人の親孝行の狙いは、国家の安定だったといえます。
孔子はこの春秋戦国時代の戦乱や政治的な不安定に対し、個人の道徳と家族関係を基盤とした社会秩序の回復を提案しました。
その中でも「孝」は家庭内での和を保つ基本的な道徳として強調されました。
親への孝行は家庭内の平和を築くだけでなく、社会全体の安定にも寄与するということなのです。
「家族」という最小単位の秩序が整えば、それが国家全体の秩序に繋がります。
この考え方は、儒教がその後の中国の国家体制に取り入れられることでさらに発展しました。
「孝」の具体的な教え
儒教の経典である『孝経』には、親孝行について次のような教えが記されています。
「身体髪膚(しんたいはっぷ)は父母に受く、敢えて毀傷(きしょう)せざるは孝の始めなり」
これは「私たちの身体はすべて親から受け継いだものであり、それを傷つけることなく大切にすることが親孝行の第一歩である」という意味です。
また、親が生きている間は親の意志に従い、亡くなった後も礼を尽くして供養を行うことが孝の重要な側面とされています。
このような教えは、長い間東アジアの文化や風習に影響を与えてきました。
親孝行の教えが広がった背景
儒教が中国をはじめとする東アジア各地に広がる中で、「親孝行」という価値観は人々の生活の中に深く根付いていきました。
その背景には、儒教が国家統治のイデオロギーとして利用されたという側面があります。
皇帝や支配者たちは、儒教の親孝行の教えを通じて、家族間の忠誠心を国家への忠誠心に結びつけました。
このようにして、親孝行は個人の道徳的な行いであると同時に、社会全体の安定を保つための重要な手段として位置付けられるようになったのです。
毒親にしたがう必要はあるのか
親孝行について深く考えていると、毒親にもしたがう必要があるのかという疑問が出てきます。
本稿では、毒親の特徴や親孝行という概念の背景を踏まえ、「毒親にしたがう必要があるのか」というテーマを掘り下げていきます。
毒親の特徴
- 過干渉…子どもの生活全般に過剰に干渉し、子どもの自立を妨げる親。たとえば、進路や交友関係、さらには結婚まで強制的に決めようとするケースが該当する。
- 過剰な批判や否定…子どもの意見や行動を否定し続ける親。これにより、子どもは自己肯定感を失い、自分の判断に自信を持てなくなる。
- 身体的・精神的虐待…暴力を振るったり、言葉で傷つけたりする親。場合によっては、子どもに過剰な期待をかけ、失敗を許さない姿勢を取ることもある。
毒親に育てられた子どもは、精神的な傷を抱え、大人になっても親の影響から抜け出せないことが多いです。そのため、毒親に対してしたがうべきかという問題は、非常に深刻です。
親孝行の歴史的背景
儒教における親孝行の教えは、家庭内の秩序を保つために強調されたものであり、社会や国家の安定に寄与することを目的としていました。
この教えの中では、親は子どもに対して無条件に敬われるべき存在とされています。
しかし、このような考え方は、必ずしも親が正しい行動を取ることを保証するものではありません。
儒教が生まれた時代には、親が子どもを守り、導くという前提がありました。
しかし、現代社会では、親であっても必ずしも正しい価値観や行動を持つとは限りません。
このように、毒親の存在は、この前提を根底から覆すものであり、従来の親孝行の概念を見直す必要性を提起しているのです。
毒親に従う必要はない理由
毒親に従わなければならないと考える人は、以下のようなプレッシャーを抱えていることが多いです。
毒親育ちが受ける様々なプレッシャー
- 「親を敬うべき」という社会的プレッシャー…親孝行を重視する文化では、「親に逆らうのは良くない」とされる。しかし、この考え方は、親が子どもに正しい態度で接している場合にのみ適用されるべきである。毒親に無条件で従うことは、子どもの人生や幸福を犠牲にする危険性がある。
- 罪悪感の刷り込み…多くの毒親は、子どもに「親に従わないのは悪いことだ」と罪悪感を植え付ける。しかし、子どもが親の期待に応えるために自分の意志を抑えることは、自己実現を阻害する結果につながる。
子どもの人生は子どものものであり、子どもは親の所有物ではありません。
そして、子どもが自分の人生を自由に選択し、幸福を追求する権利は、誰にも侵害されるべきではないのです。
であるから、毒親に従うことがその権利を侵害する場合、従わない選択をすることは正当です。
ただし、毒親にしたがう必要がないのは、成人している場合です。
養育を受けている場合はしたがわなければなりません。
したがいたくない場合は、自分で生活を成り立たせ、親の扶養からはずれる必要があります。
毒親との距離のとり方
- 心理的な距離を取る…必要以上に親の言葉を真に受けないようにし、自分自身の価値観を大切にする。
- 物理的な距離を取る…親と離れて暮らすことで、自分の生活を守る。これにより、親の影響を最小限に抑えることができる。
なぜ毒親にしたがう必要があるのかといえば、国家の統制のためです。
皇帝がそれぞれの国の王をしたがえ、それぞれの国の王が村々の長老をしたがえ、それぞれの長老が家父長をしたがえ、それぞれの家父長が家族をしたがえ…というふうに、子どもが親孝行だと家族や国の統制がとれるのです。
しかし、今では毒親にしたがうべきかという問題は、個人の幸福を最優先に考えるべきです。
親孝行は尊い価値観であるが、それが子どもの人生を犠牲にしてまで実践されるべきものではないのです。
毒親との関係に悩む人は、自分自身の権利と幸福を守るために適切な距離を保つ選択を検討するべきです。
昔の中国でさえも、おかしい親にしたがうべきかという論争がありました。
そして、したがうべきではないという結論に至りました。
親孝行は国家統制のための教えであり個人の幸せのためではない
「親孝行」という言葉は、日本を含む東アジアの文化において美徳とされてきました。
しかし、今までみてきたように、その背景を探ると、親孝行が必ずしも個人の幸せを目的とした教えではないことがみえてきます。
「親孝行」という言葉は、家庭内で親に従順であることを義務付けることで、国民が支配者に対しても従順であるように仕向ける狙いがありました。
家族を統制することで国家全体を統制するというこの考え方は、古代中国の皇帝や封建支配者たちにとって非常に都合の良いものでありました。
親孝行が国家統制のための教えとして機能してきた一方で、それが必ずしも個人の幸せに繋がるわけではありません。
親孝行と個人の幸せとの矛盾
- 親の意志が絶対視されること親孝行を重視する文化では、親の意志が絶対的なものとして扱われる傾向がある。これにより、子どもは自分の夢や目標を諦めて親の期待に応えることを強いられる場合がある。このような状況は、子どもの自己実現や幸せを妨げる結果に繋がる。
- 親子関係の固定化親孝行を強調することで、親と子どもの関係が固定化され、対等な関係を築くことが難しくなる。子どもが大人になっても親に従順であることが求められるため、独立した個人としての幸福が制限される可能性がある。
- 毒親問題との関係親が必ずしも善意を持って子どもに接するとは限らない。いわゆる「毒親」に育てられた子どもにとって、親孝行は自己犠牲を強いる不公平な教えとして機能する。この場合、親孝行を実践することは子どもにとって苦痛でしかない。
このように、親孝行は国家統制のための教えで、個人の幸福のための教えではありません。
今の時代は個人の幸福の追求の時代だから、個人の幸福を犠牲にしてまでおかしい親にしたがう必要はありません。




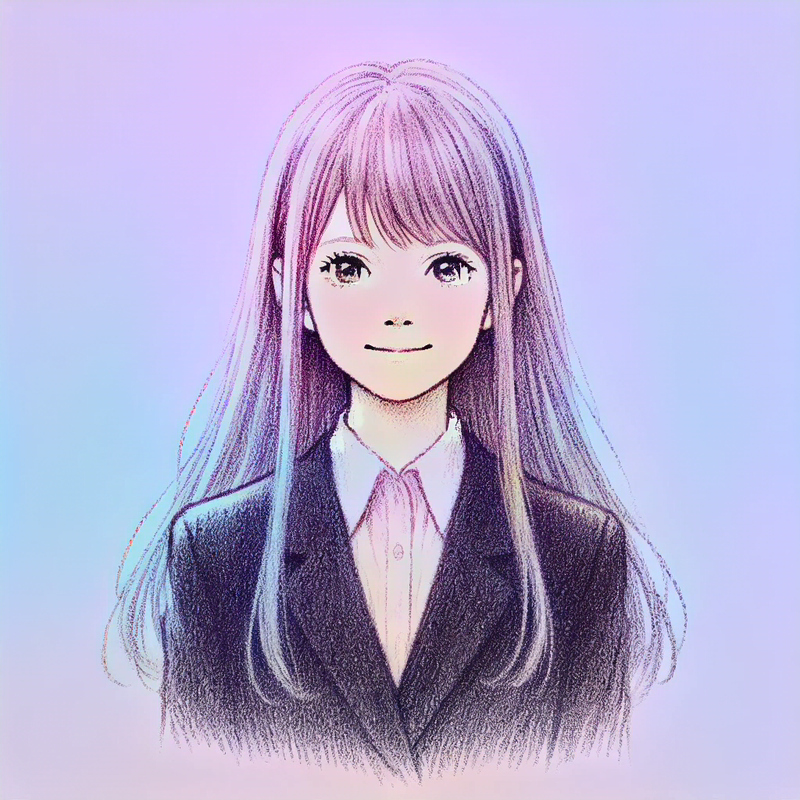








コメント
コメント一覧 (4件)
[…] 親孝行は国家統制のための教えであり個人の幸せのためではない 親孝行という言葉に苦しめられてはいないだろうか。 […]
[…] 親孝行は国家統制のための教えであり個人の幸せのためではない 親孝行という言葉に苦しめられてはいないだろうか。 […]
[…] あわせて読みたい 親孝行は国家統制のための教えであり個人の幸せのためではない 親孝行という言葉に苦しめられてはいないだろうか。 […]
[…] 仏教と儒教では、親… あわせて読みたい 親孝行は国家統制のための教えであり個人の幸せのためではない 親孝行という言葉に苦しめられてはいないだろうか。 […]